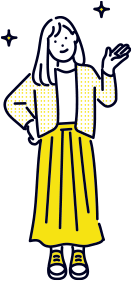国・地域から調べる
留学先の国の特徴や留学情報をご紹介。
国ごとの違いを明確に知り、自分にあった留学先を見つけましょう。

アメリカ合衆国
体験レポート


留学先国・地域:アメリカ合衆国・ニューハンプシャー州
学校名:Dartmouth College
専攻名:Integrative Neuroscience at Dartmouth
留学期間:2023年8月~2028年6月(予定)
留学形態:博士課程への進学
奨学金:JASSO給付型「海外留学支援制度(大学院学位取得型)」
学校名:Dartmouth College
専攻名:Integrative Neuroscience at Dartmouth
留学期間:2023年8月~2028年6月(予定)
留学形態:博士課程への進学
奨学金:JASSO給付型「海外留学支援制度(大学院学位取得型)」
留学の動機について
Q. 留学をしようと思った動機を教えてください。
アメリカでの留学(博士号取得)については、心理学で一般的に使われている実験手法では答えられなかった多くの「なぜ」という疑問に取り組みたいという、私の思いの結果です。
コロナウイルスの影響により、3年の留学生活の大半を日本の家の中で過ごしていたことで、心理学の学位を取得した後も、自分がどのようなキャリアに進めるのか分からずにいました。幸いなことに、偶々興味を持ったシナプス形成の細胞メカニズムを研究するラボの研究室で、リサーチ・アシスタントとして受け入れてもらえることが決まったため、新たな分野の勉強を始めることにしました。そこでは、神経科学と心理学で実験の設計がどのように異なるのかを学び、人間の行動を生み出すプロセスに、これほどまでに近づくことができることに衝撃を受けました。これまで培った心理学と神経科学の知見を活かし、発達の根底にあるシナプス形成のメカニズムについて研究するとともに、トランスレーション研究に携わることが出来る幅広い知識やスキルを身につけたいと思いました。
Q. 留学先の国・地域、留学先校を選んだ理由を教えてください。
アメリカの科学研究の環境は、学生への資金提供の規模や、研究を推進する科学コミュニティの大きさの点で、他に類を見ない素晴らしさがあります。私は、知的な人々が集まり、分野横断的に協力し合える環境で学ぶことに憧れていました。
また、これまでずっと都市部で育ってきたため、自然に囲まれ、自然を愛する人々がいる田舎で生活することにも魅力を感じていました。ダートマス大学は小規模な大学ですが、結束の強いコミュニティがあります。オープンキャンパスで訪問した際、その神経科学コミュニティに接した時に、とても良い印象を受けました。これが、このプログラムを選択した理由です。
Q. 留学に対する家族の反応はどうでしたか。
留学に対するの最初のハードルは、海外で心理学を学ぶために、イギリスの大学へ行くことを決めた時でした。反対の主な理由は経済的なもので、当時のキャリア目標(海外の臨床心理士)に照らして、高額すぎる学費を正当化しなければなりませんでした。
博士課程については、学費免除付きで合格することができましたが、その生活費は決して安価ではなく、特にアッパーバレーでの住宅事情の悪さを考えると大きな負担でした。神経科学を学ぶためにアメリカに渡るには、経済的に自立することが条件であり、JASSOの支援なしでは実現できなかったと思います。
アメリカでの留学(博士号取得)については、心理学で一般的に使われている実験手法では答えられなかった多くの「なぜ」という疑問に取り組みたいという、私の思いの結果です。
コロナウイルスの影響により、3年の留学生活の大半を日本の家の中で過ごしていたことで、心理学の学位を取得した後も、自分がどのようなキャリアに進めるのか分からずにいました。幸いなことに、偶々興味を持ったシナプス形成の細胞メカニズムを研究するラボの研究室で、リサーチ・アシスタントとして受け入れてもらえることが決まったため、新たな分野の勉強を始めることにしました。そこでは、神経科学と心理学で実験の設計がどのように異なるのかを学び、人間の行動を生み出すプロセスに、これほどまでに近づくことができることに衝撃を受けました。これまで培った心理学と神経科学の知見を活かし、発達の根底にあるシナプス形成のメカニズムについて研究するとともに、トランスレーション研究に携わることが出来る幅広い知識やスキルを身につけたいと思いました。
Q. 留学先の国・地域、留学先校を選んだ理由を教えてください。
アメリカの科学研究の環境は、学生への資金提供の規模や、研究を推進する科学コミュニティの大きさの点で、他に類を見ない素晴らしさがあります。私は、知的な人々が集まり、分野横断的に協力し合える環境で学ぶことに憧れていました。
また、これまでずっと都市部で育ってきたため、自然に囲まれ、自然を愛する人々がいる田舎で生活することにも魅力を感じていました。ダートマス大学は小規模な大学ですが、結束の強いコミュニティがあります。オープンキャンパスで訪問した際、その神経科学コミュニティに接した時に、とても良い印象を受けました。これが、このプログラムを選択した理由です。
Q. 留学に対する家族の反応はどうでしたか。
留学に対するの最初のハードルは、海外で心理学を学ぶために、イギリスの大学へ行くことを決めた時でした。反対の主な理由は経済的なもので、当時のキャリア目標(海外の臨床心理士)に照らして、高額すぎる学費を正当化しなければなりませんでした。
博士課程については、学費免除付きで合格することができましたが、その生活費は決して安価ではなく、特にアッパーバレーでの住宅事情の悪さを考えると大きな負担でした。神経科学を学ぶためにアメリカに渡るには、経済的に自立することが条件であり、JASSOの支援なしでは実現できなかったと思います。
留学の準備について
Q. 留学の準備にはどのくらいの期間を要しましたか。
PhD進学を決意したのは、留学の1年前です。
この奨学金を知ったのは、秋の博士課程出願シーズンの前、夏の初めのことでした。その年の初めから、以前から興味のあったプログラムについて調べ始め、各大学の大学院生に連絡し、出願プロセスやアドバイスについてオンラインで話を伺いました。彼らが共有してくれたアドバイスや資料のおかげで、全米各地でいくつかの面接を受ける機会を得ることができました。
翌年の春(3月中旬)に2つの面接を受け、1週間以内に進学先を決定。その後すぐにビザ申請と住居探しを始めました。幸いなことにすべて順調に進み、その年の初夏には、ビザと住居も確保することができていました。
各準備段階の時系列(目安):
・情報収集・学校選定:前年の夏ごろから開始(約1年ほど前)
・出願準備・面接:秋~翌年春(出願は秋、面接は春)
・合格校決定・進学手続き:春(面接後すぐ、3月中旬~下旬)
・ビザ申請・住居探し:春~初夏(4月~6月ごろ)
・出発:夏(8月以降)
Q. 留学情報の収集はどのように行っていましたか。
主に各大学やプログラムの公式ウェブサイトから、その雰囲気や情報を収集していました。また、実際に在籍している大学院生にコンタクトを取り、プログラムの実情や生活について直接話を聞く機会も多くありました。
情報収集は、YouTubeで博士課程の学生によるブイログなどで出願を希望するプログラムを絞って行き、最終的には、出願を希望するプログラムで実際に学んでいる先輩方と話をする中で、今後の5年間の生活や研究がどのようなものかを具体的に掴んでいきました。
Q. 留学中の住まいはどのように探しましたか。
プログラムの先輩方からのアドバイスを参考に、最初の1年目はダートマスの大学院生や専門職学生向けに新しく建設されたアパートメントに住みました。家賃は希望よりもやや高めでしたが、申し込み手続きがシンプルで、部屋の割り当てもランダムだったため、他のさまざまな留学準備に追われている時期でも手間が少なく、とても助かりました。もしこのアパートを利用しなかった場合は、地域に数少ない賃貸プラットフォームを利用して物件を探さなければならず、実際に内見せずに物件を決めることに躊躇いがありました。
Q. 語学学習はどのように行っていましたか。
育った環境もあり、私は語学面で特別な対策をする必要はありませんでしたが、大学院コミュニティには英語がそれほど得意ではない友人もいます。彼らの場合、面接の際に自分の研究に対する情熱や、コミュニティの文化的多様性に貢献したいという姿勢をしっかり伝えられていたのだと思います。
Q. 留学にはどのくらい費用がかかりましたか。留学の資金調達はどのように行いましたか。
イギリスでの学部生時代は、親の援助と、アルバイトで生活をしていました。その後のPhD進学については、学部卒業後の2年間、リサーチアシスタントとして働いていたので、その間に貯めたお金を、アメリカの博士課程への進学資金に充てました。
Q. 入学や学生登録の手続き、ビザの手続きなどはどのように行いましたか。</br>特に苦労したことや気を付けたほうがいいことなどが教えてください。
ビザ申請(特に現在のアメリカの情勢では)は、進学先が決まり次第、早めに申請をすることをお勧めします。簡単な面接もあり、プログラムの内容やアメリカで学ぶ目的について質問を受けました。F1ビザについてのブログ記事などを事前に調べておくと安心だと思います。
PhD進学を決意したのは、留学の1年前です。
この奨学金を知ったのは、秋の博士課程出願シーズンの前、夏の初めのことでした。その年の初めから、以前から興味のあったプログラムについて調べ始め、各大学の大学院生に連絡し、出願プロセスやアドバイスについてオンラインで話を伺いました。彼らが共有してくれたアドバイスや資料のおかげで、全米各地でいくつかの面接を受ける機会を得ることができました。
翌年の春(3月中旬)に2つの面接を受け、1週間以内に進学先を決定。その後すぐにビザ申請と住居探しを始めました。幸いなことにすべて順調に進み、その年の初夏には、ビザと住居も確保することができていました。
各準備段階の時系列(目安):
・情報収集・学校選定:前年の夏ごろから開始(約1年ほど前)
・出願準備・面接:秋~翌年春(出願は秋、面接は春)
・合格校決定・進学手続き:春(面接後すぐ、3月中旬~下旬)
・ビザ申請・住居探し:春~初夏(4月~6月ごろ)
・出発:夏(8月以降)
Q. 留学情報の収集はどのように行っていましたか。
主に各大学やプログラムの公式ウェブサイトから、その雰囲気や情報を収集していました。また、実際に在籍している大学院生にコンタクトを取り、プログラムの実情や生活について直接話を聞く機会も多くありました。
情報収集は、YouTubeで博士課程の学生によるブイログなどで出願を希望するプログラムを絞って行き、最終的には、出願を希望するプログラムで実際に学んでいる先輩方と話をする中で、今後の5年間の生活や研究がどのようなものかを具体的に掴んでいきました。
Q. 留学中の住まいはどのように探しましたか。
プログラムの先輩方からのアドバイスを参考に、最初の1年目はダートマスの大学院生や専門職学生向けに新しく建設されたアパートメントに住みました。家賃は希望よりもやや高めでしたが、申し込み手続きがシンプルで、部屋の割り当てもランダムだったため、他のさまざまな留学準備に追われている時期でも手間が少なく、とても助かりました。もしこのアパートを利用しなかった場合は、地域に数少ない賃貸プラットフォームを利用して物件を探さなければならず、実際に内見せずに物件を決めることに躊躇いがありました。
Q. 語学学習はどのように行っていましたか。
育った環境もあり、私は語学面で特別な対策をする必要はありませんでしたが、大学院コミュニティには英語がそれほど得意ではない友人もいます。彼らの場合、面接の際に自分の研究に対する情熱や、コミュニティの文化的多様性に貢献したいという姿勢をしっかり伝えられていたのだと思います。
Q. 留学にはどのくらい費用がかかりましたか。留学の資金調達はどのように行いましたか。
イギリスでの学部生時代は、親の援助と、アルバイトで生活をしていました。その後のPhD進学については、学部卒業後の2年間、リサーチアシスタントとして働いていたので、その間に貯めたお金を、アメリカの博士課程への進学資金に充てました。
Q. 入学や学生登録の手続き、ビザの手続きなどはどのように行いましたか。</br>特に苦労したことや気を付けたほうがいいことなどが教えてください。
ビザ申請(特に現在のアメリカの情勢では)は、進学先が決まり次第、早めに申請をすることをお勧めします。簡単な面接もあり、プログラムの内容やアメリカで学ぶ目的について質問を受けました。F1ビザについてのブログ記事などを事前に調べておくと安心だと思います。
留学中の様子について
Q. 留学中の学校生活はどうでしたか。日本の学校との違いや、海外の学校だからこそ苦労すること、学校生活での楽しみなどを教えてください。
アメリカ博士課程の魅力のひとつは、教員陣との質の高い交流ができること、そして国内の科学コミュニティの規模の大きさでした。休憩室で、自分の研究テーマとはまったく関係のない科学の話を教員と交わすこともあれば、多様な聴衆の前で自分の研究を発表したり、異分野の仲間からの創造的なアイデアに刺激を受けたりする機会にも恵まれます。最近では、ティーチングアシスタントとして海洋生物学研究所(Marine Biological Laboratory)に3週間滞在し、国内各地の大学や研究機関から集まった大学院生・ポスドク研究者や著名な教員と知り合うことができました。科学者たちのエネルギーや情熱を肌で感じることは常に励みとなり、博士課程の厳しい時期であっても、私を研究室に向かわせる原動力となっています。
Q. 学校外の生活はどうでしたか。寮などでの生活や休日の過ごし方、町の治安などについても教えてください。
人生のほとんどを都会で過ごしてきた私にとって、車を持たず森の中で暮らすことは、大きな変化でした。ここに越して来てからは、ヨーロッパで1週間のハイキングを楽しんだり、早朝4時に起床し、山頂で日の出を見たりと、アクティブなことを楽しむ友人たちに囲まれた生活を送っています。初めての冬にはハイキング好きの友人からアイゼン(雪の上を歩くための靴底に装着する登山道具)を借りて6時間ほど雪山を歩いたり、友人の車に同乗してキャンパスから北へ2時間かけて流星群を見に行ったり、気まぐれで土曜日の朝にDiner hopping(カジュアルな飲食店を巡って食事を楽しむ)に出かけたりもしました。
この地域では公共交通機関が限られているため自由に移動できるようになりたいと思い、運転の練習もしていますが、普段は無料のバスを利用して大学と自宅を往復しています。街には、大学生や犬、フレンドリーなお年寄りが多く、夜遅く、深夜を過ぎても安心して歩けるほど治安はとても良いです。
Q. 留学中の生活で大変だったことを教えてください。また、それをどのように克服、対応しましたか。
一番大変だったのは、新しい研究室で新しい指導教員のもと、Qualifying Exam に臨んだことでした。私は指導教員にとって初めての博士課程の学生であり、私自身も指導教員も、試験がどのようなものになるのか全く予想がつきませんでした。自分で自分にプレッシャーをかけてしまう性格に加え、研究室の先輩でQualifying Exam を受けた人がいなかったため、参考にできる前例がないことも大きな不安要素でした。それでもなんとか乗り越え、振り返ってみれば、結局あらゆる質問に備えることなど不可能だったと気づきました。次に試験を受ける研究室の後輩には、不安になりすぎて睡眠を削るようなことはしないようにと伝えています(笑)
アメリカ博士課程の魅力のひとつは、教員陣との質の高い交流ができること、そして国内の科学コミュニティの規模の大きさでした。休憩室で、自分の研究テーマとはまったく関係のない科学の話を教員と交わすこともあれば、多様な聴衆の前で自分の研究を発表したり、異分野の仲間からの創造的なアイデアに刺激を受けたりする機会にも恵まれます。最近では、ティーチングアシスタントとして海洋生物学研究所(Marine Biological Laboratory)に3週間滞在し、国内各地の大学や研究機関から集まった大学院生・ポスドク研究者や著名な教員と知り合うことができました。科学者たちのエネルギーや情熱を肌で感じることは常に励みとなり、博士課程の厳しい時期であっても、私を研究室に向かわせる原動力となっています。
Q. 学校外の生活はどうでしたか。寮などでの生活や休日の過ごし方、町の治安などについても教えてください。
人生のほとんどを都会で過ごしてきた私にとって、車を持たず森の中で暮らすことは、大きな変化でした。ここに越して来てからは、ヨーロッパで1週間のハイキングを楽しんだり、早朝4時に起床し、山頂で日の出を見たりと、アクティブなことを楽しむ友人たちに囲まれた生活を送っています。初めての冬にはハイキング好きの友人からアイゼン(雪の上を歩くための靴底に装着する登山道具)を借りて6時間ほど雪山を歩いたり、友人の車に同乗してキャンパスから北へ2時間かけて流星群を見に行ったり、気まぐれで土曜日の朝にDiner hopping(カジュアルな飲食店を巡って食事を楽しむ)に出かけたりもしました。
この地域では公共交通機関が限られているため自由に移動できるようになりたいと思い、運転の練習もしていますが、普段は無料のバスを利用して大学と自宅を往復しています。街には、大学生や犬、フレンドリーなお年寄りが多く、夜遅く、深夜を過ぎても安心して歩けるほど治安はとても良いです。
Q. 留学中の生活で大変だったことを教えてください。また、それをどのように克服、対応しましたか。
一番大変だったのは、新しい研究室で新しい指導教員のもと、Qualifying Exam に臨んだことでした。私は指導教員にとって初めての博士課程の学生であり、私自身も指導教員も、試験がどのようなものになるのか全く予想がつきませんでした。自分で自分にプレッシャーをかけてしまう性格に加え、研究室の先輩でQualifying Exam を受けた人がいなかったため、参考にできる前例がないことも大きな不安要素でした。それでもなんとか乗り越え、振り返ってみれば、結局あらゆる質問に備えることなど不可能だったと気づきました。次に試験を受ける研究室の後輩には、不安になりすぎて睡眠を削るようなことはしないようにと伝えています(笑)

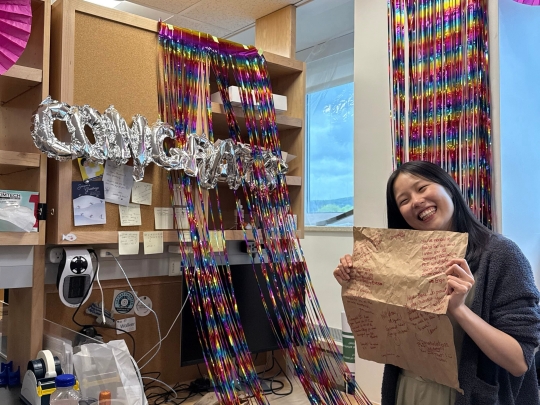
留学後について
Q. 留学を経験してみて感じたこと、学んだことはありますか。留学前と比べて成長した面はありますか。
自分の限界に挑戦し、興味のある分野を追求することに強く惹かれていましたが、今振り返ると、博士課程に対して理想化したイメージを持っていたことに気付きました。現実には、夜遅くまで作業したり、何ヶ月も実験のトラブル対応に追われたり、週の大半の時間を、机に向かって論文を読むことに費やすような時も多々あります。それでも、学問的にも精神的にも支えてくれる指導教員や仲間に恵まれ、ダートマスのコミュニティの刺激的で励ましてくれる環境が、今の自身の成果に大きく貢献していると感じています。この博士課程を通して、金曜日の夜や月曜日の朝も苦にならず、前向きに取り組めるようになったことは、以前の自分と比べて大きな成長だと思います。
Q. 留学後の進路について教えてください。
アカデミア以外のキャリアに傾きつつありますが、具体的にどのような職種に就くかはまだ決めていません。まだ博士課程の半分に到達していない段階で、決めるべきではないかなとも思っています。
現在は、STEM分野で活躍する女性を支援する団体や、若い学生に向けて科学アウトリーチを行うグループに参加しているほか、大学院のバイオテッククラブのメンバーでもあることから、研究成果を広く社会に伝えたり、異なるバックグラウンドを持つ人々をつなげたりすることにやりがいを感じており、何らかの形で、科学と社会の架け橋になれればいいなと考えています。研究プロジェクトの枠を超えてこうした活動に取り組む中で多様な経験を積み、少しずつ、キャリアの方向性を明確にしていきたいと思います。
Q. 最後にこれから留学をする方へのメッセージ・アドバイスをお願いします。
海外で学位を取得することは大きな挑戦ですが、同時にとても貴重な機会でもあります。私が所属するコミュニティの学問文化で好きな点は、目標達成のために機会を探し、リソースを求める人を惜しみなくサポートしてくれるところです。その意味で、留学の経験は人それぞれ異なりますが、みなさんもぜひこの素晴らしい機会を存分に活かし、新しい発見ができることを願っています。
自分の限界に挑戦し、興味のある分野を追求することに強く惹かれていましたが、今振り返ると、博士課程に対して理想化したイメージを持っていたことに気付きました。現実には、夜遅くまで作業したり、何ヶ月も実験のトラブル対応に追われたり、週の大半の時間を、机に向かって論文を読むことに費やすような時も多々あります。それでも、学問的にも精神的にも支えてくれる指導教員や仲間に恵まれ、ダートマスのコミュニティの刺激的で励ましてくれる環境が、今の自身の成果に大きく貢献していると感じています。この博士課程を通して、金曜日の夜や月曜日の朝も苦にならず、前向きに取り組めるようになったことは、以前の自分と比べて大きな成長だと思います。
Q. 留学後の進路について教えてください。
アカデミア以外のキャリアに傾きつつありますが、具体的にどのような職種に就くかはまだ決めていません。まだ博士課程の半分に到達していない段階で、決めるべきではないかなとも思っています。
現在は、STEM分野で活躍する女性を支援する団体や、若い学生に向けて科学アウトリーチを行うグループに参加しているほか、大学院のバイオテッククラブのメンバーでもあることから、研究成果を広く社会に伝えたり、異なるバックグラウンドを持つ人々をつなげたりすることにやりがいを感じており、何らかの形で、科学と社会の架け橋になれればいいなと考えています。研究プロジェクトの枠を超えてこうした活動に取り組む中で多様な経験を積み、少しずつ、キャリアの方向性を明確にしていきたいと思います。
Q. 最後にこれから留学をする方へのメッセージ・アドバイスをお願いします。
海外で学位を取得することは大きな挑戦ですが、同時にとても貴重な機会でもあります。私が所属するコミュニティの学問文化で好きな点は、目標達成のために機会を探し、リソースを求める人を惜しみなくサポートしてくれるところです。その意味で、留学の経験は人それぞれ異なりますが、みなさんもぜひこの素晴らしい機会を存分に活かし、新しい発見ができることを願っています。
日本学生支援機構
(JASSO)とは
独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)は、
文部科学省が所管する団体です。
学生支援を先導する中核機関として、「奨学金事業」
「留学生支援事業」および
「学生生活支援事業」を
総合的に実施し、
次世代の社会を担う豊かな
人間性を備えた創造的な人材を育成すると
ともに、
国際理解・交流の促進を図ることを目指しています。
文部科学省が所管する団体です。
学生支援を先導する中核機関として、「奨学金事業」
「留学生支援事業」および
「学生生活支援事業」を
総合的に実施し、
次世代の社会を担う豊かな
人間性を備えた創造的な人材を育成すると
ともに、
国際理解・交流の促進を図ることを目指しています。